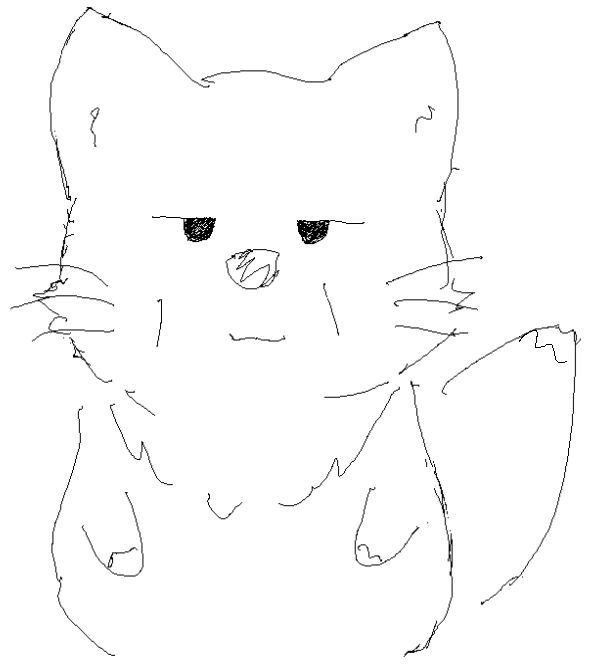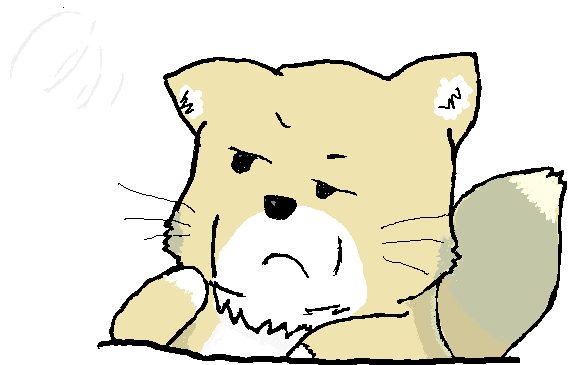― 問題 ―
医薬品は、市販後にも、その安全性の確認が行われる仕組みとなっているが、有効性についても市販後にに確認はしなければならない。
答え、①.誤り 〇
解説
医薬品は有効性や安全性が市販前に確認されますが、市販後にも確認することが必要で、副作用や健康影響が新たに発生していないか確認する必要があります。
(Tokyo,R6-AM01-modification)
― 問題 ―
医薬品は、市販後にも、その安全性の確認が行われる仕組みとなっているが、その有効性については市販前に十分確認されているため、市販後に確認は行われない。
答え、①.誤り 〇
解説
医薬品医療機器等法では、医薬品や医療機器の品質や安全を確保するために、異物混入や変質がある医薬品の販売を禁止しています。
(Tokyo,R6-AM01-modification)
― 問題 ―
健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売してはならない旨を定めているのは、医薬品医療機器等法である。
答え、①.誤り 〇
解説
医薬品医療機器等法では、医薬品や医療機器の品質や安全を確保するために、異物混入や変質がある医薬品の販売を禁止しています。
(Tokyo,R6-AM01-modification)
― 問題 ―
医薬品は、効能効果、用法用量、副作用など必要な情報が適切に伝達されなくても、購入者等が適切に使用しその役割を十分に発揮するようになっている。
答え、①.誤り ✕
解説
医薬品は、効能効果、用法用量、副作用など必要な情報が適切に伝わることで、購入者等が適切に使用し、初めてその役割を十分に発揮するものであるため、誤った使用方法では副作用などいろいろ問題が発生する。
(Tokyo,R6-AM01-modification)
― 問題 ―
医薬品は、製造販売業者よる製品回収等の措置がなされることがあるので医薬品は販売等を行う物は、気にせず販売しても問題はない。
答え、①.誤り ✕
解説
医薬品は、製造販売業者よる製品回収等の措置がなされることがあるので医薬品は販売等を行う物は、製造販売業者などから情報に日頃から留意する必要があります。
(Tokyo,R6-AM01-modification)
― 問題 ―
シロップ剤は変質しやすいため、開封後は冷蔵庫での保管が適当である。
答え、①.正しい 〇
解説
医薬品は間違った保管をすると雑菌繁殖や化学変化等を生じるため適切な保管が大事である。
― 問題 ―
錠剤・散剤・カプセル剤等は室温での保管が適当である。
答え、①.正しい 〇
解説
冷蔵庫で保管すると、取り出したときに室温との急な温度差で湿気を帯びる可能性があるため不適である。
― 問題 ―
妊娠検査薬の添付文書には検出感度の記載が必要である。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
一般用医薬品の添付文書は、医薬品の安全性や有効性等の新たな知見や使用情報に基づいて必要に応じ随時改定されている。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
グッズ等の景品類を付けて医薬品を販売することにおいて、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
答え、①.正しい 〇
解説
ただし、医薬品を景品や懸賞商品として授与することは原則認められていない。
― 問題 ―
濫用等の恐れがあるとして厚生労働大臣が指定する医薬品には、エフェドリン・コデイン・ブロモバレリル尿素などがある。
答え、①.正しい 〇
解説
その他に、ジヒドロコデイン・プソイドエフェドリン・メチルエフェドリンがある。
― 問題 ―
一般用医薬品のうち濫用等の恐れがあるとして厚生労働大臣が指定する医薬品を購入および譲り受ける者が若年者の場合に、薬剤師または登録販売者は当該者の氏名と年齢を確認する必要がある。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
薬局開設者・店舗販売者・配置販売業者は、その薬局・店舗・区域において医薬品販売等に従事する薬剤師・登録販売者または一般従事者であることが容易に判別出来る様に名札着用等の必要な措置をとらなければならない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する"情報提供を行うための設備(例:販売カウンター等)"から5m以内の範囲に陳列しなければならない。
答え、②.誤り ✕
解説
7m以内の範囲に陳列しなければならない。
― 問題 ―
要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画内部の陳列設備に、第一類医薬品は第一類医薬品陳列区画内部の陳列設備にそれぞれ陳列しなければならない。
答え、①.正しい 〇
解説
ただし、どちらも鍵をかけた陳列設備に陳列する場合、または購入者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合はその限りでない。
― 問題 ―
要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品のうち、登録販売者が対応できるのは第二類および第三類医薬品である。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
配置販売業者及び配置員が持つ身分証明書の有効期限は、発行日から発行日の属する年の翌年の12月31日までである。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
店舗販売業では薬剤師がいても調剤は出来ず、また、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し。
― 問題 ―
薬局は薬剤師でなくても開設できる。
答え、①.正しい 〇
解説
薬局開設者が薬剤師でない場合、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、現場で実際に管理しなければならない。
― 問題 ―
薬局を開設したい場合、その所在地の都道府県知事の許可が必要である。
答え、①.正しい 〇
解説
開設したい所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合においては、市長または区長の許可が必要である。
― 問題 ―
薬局・卸売販売業・店舗販売業では、特定の購入者の求めがあれば、医薬品の包装を開封し分割販売をおこなえる。
答え、①.正しい 〇
解説
分割販売ができるからといって、予め医薬品を小分け販売する行為は無許可製造および無許可製造販売にあたるため認められていない。
― 問題 ―
医薬品を販売するためには、3種類の医薬品の販売業の許可または薬局の開設の許可を受ける必要がある。
答え、①.正しい 〇
解説
医薬品販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類がある。
― 問題 ―
マグネシウムは多量摂取により軟便(下痢)になる場合がある。
答え、①.正しい 〇
解説
多量摂取により疾病の治癒、及び健康が増進することはないため1日の摂取目安量を守るべきである。
― 問題 ―
医薬品・医薬部外品・化粧品のうち、医薬品と医薬部外品は厚生労働大臣が指定するものを除き品目ごとの承認が必要となる。
答え、①.正しい 〇
解説
化粧品は、厚生労働大臣が指定するものは承認が必要となるが、大部分はあらかじめ品目ごとに届出を行う必要がある。
― 問題 ―
配置販売品目以外の一般用医薬品は、直接の容器または被包に"店舗専用"の文字が記載されていなければならない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し
― 問題 ―
指定第二類医薬品は直接の容器または被包に、枠の中に"2"の数字が記載されていなければならない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し
― 問題 ―
指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、厚生労働大臣が特別な注意を要するものとして指定したもののことである。
答え、①.正しい 〇
解説
指定第二類医薬品の例として咳止めシロップがある。
― 問題 ―
毒薬劇薬を販売または譲渡する際には譲渡文書が必要で、記載する氏名は譲り受ける人物の氏名である。
答え、①.正しい 〇
解説
その他の記載事項として、品名・数量・使用目的・譲渡年月日・譲り受ける者の住所職業・譲り受ける者の署名または記名押印がある。
― 問題 ―
日本薬局方に収められているものは、すべて医薬品である。
答え、①.正しい 〇
解説
日本薬局方に収載されている医薬品の中には、一般用医薬品として販売されているもの、または一般用医薬品中に配合されているものも少なくない。
― 問題 ―
登録販売者は、登録販売者名簿の登録事項に変更が生じた場合は30日以内にその旨を届けねばならない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し
― 問題 ―
殺菌消毒薬を誤飲した場合、応急処置として多量の牛乳を飲むとよい。
答え、①.正しい 〇
解説
牛乳がない場合は代わりに水を飲ませるとよい。
― 問題 ―
肥満の時に処方される漢方処方製剤の防已黄耆湯は、水太りのときの肥満で処方される。
答え、①.正しい 〇
解説
同じ肥満でも防風通聖散は、腹部に皮下脂肪が多いときの肥満で処方される。
― 問題 ―
漢方処方製剤は生後3ヶ月未満の乳児に使用してはならない。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し
― 問題 ―
滋養強壮保健薬に配合されている成分の1つであるグルクロノラクトンには、肝臓の血流を促進する特徴がある。
答え、①.正しい 〇
解説
肝血流促進によって肝臓の働きが助けられるので、疲労時や全身倦怠感時の栄養補給を目的に配合されている。
― 問題 ―
歯槽膿漏の内服薬に使われているフィトナジオン(K1)には、炎症を起こした歯周組織からの出血を抑制する働きがある。
答え、①.正しい 〇
解説
フィトナジオンの他、カルバゾクロムにも止血作用がある。
― 問題 ―
歯槽膿漏の外用薬の組織修復成分にはアラントインが使われている。
答え、①.正しい 〇
解説
アラントインは歯槽膿漏薬において炎症を起こしている歯周組織の修復を促す。
アラントインはその他に、外用痔疾用薬では痔による肛門部創傷の治癒を、眼科用薬では眼粘膜の組織修復を促す成分として使われている。
― 問題 ―
歯槽膿漏の外用薬に使われている殺菌消毒成分にはセチルピリジニウム塩化物がある。
答え、①.正しい 〇
解説
その他の殺菌消毒成分としてチモール・イソプロピルメチルフェノールがあり、いずれにも歯肉溝の細菌繁殖を抑制する。
― 問題 ―
外用歯痛薬の殺菌消毒成分はオイゲノールである。
答え、①.正しい 〇
解説
オイゲノールには、齲蝕部位における細菌繁殖を抑制する働きがある。
― 問題 ―
抗菌作用をもつ成分であるバシトラシンの特徴として、細菌の細胞壁合成を阻害するというものがある。
答え、①.正しい 〇
解説
文章そのままのため解説無し
― 問題 ―
ヘパリン類似物質成分は、患部局所の血行を促進し血液凝固を抑制する働きを持つ。
答え、①.正しい 〇
解説
その他に保湿作用・抗炎症作用もある。
― 問題 ―
外皮用薬に使われるステロイド性抗炎症成分は、体の一部分に生じたかぶれや皮膚炎等の一時的皮膚症状の緩和が対象である。
答え、①.正しい 〇
解説
よって、広範囲に生じている皮膚症状及び慢性皮膚症状への使用は対象外となる。
― 問題 ―
傷口等の殺菌消毒成分であるヨウ素系殺菌消毒成分の特徴として、ヨウ素の殺菌力は酸性下で低下するというものがある。
答え、②.誤り ✕
解説
ヨウ素の殺菌力はアルカリ性下で低下するため、石鹸等と併用する際は石鹸成分をよく洗い落としてから使用するとよい。
― 問題 ―
眼科用薬の配合成分であるスルファメトキサゾール(サルファ剤)は、細菌・ウイルス・真菌と全ての感染に対して効果がみられる。
答え、②.誤り ✕
解説
細菌感染による化膿性の症状の改善を目的とした成分であるため、ウイルス及び真菌感染には効果がない。
― 問題 ―
スプレー式鼻炎用点鼻薬は、使用前にきちんと鼻をかんでから使用するとよい。
答え、①.正しい 〇
解説
噴霧後に鼻汁とともに逆流する可能性があるため、スプレー式鼻炎用点鼻薬を使用する際は使用前にきちんと鼻をかんでから使用することが推奨されている。
― 問題 ―
アレルギー反応の流れとして、アレルゲンが粘膜や皮膚から体内に入り込むと、その物質を特異的に認識したヒスタミンにより肥満細胞が刺激される。
答え、②.誤り ✕
解説
物質を特異的に認識するのは免疫グロブリン(抗体)である。
― 問題 ―
泌尿器用薬として処方される漢方製剤において、体力に関わらず処方できるのは牛車腎気丸、体力中等度以上に処方できるのは八味地黄丸である。
答え、②.誤り ✕
解説
体力に関わらず処方できるのは猪苓湯、体力中等度以上に処方できるのは竜胆瀉肝湯である。
牛車腎気丸、八味地黄丸は体力中等度以下に処方でき、その他に六味丸がある。
― 問題 ―
外用痔疾用薬に配合されている鎮痒成分であるカンフルは、熱感刺激により痒みを抑える効果がある。
答え、②.誤り ✕
解説
熱感刺激の効果があるのはクロタミトンであり、カンフルは冷感刺激の効果がある。
その他に冷感刺激の効果がある成分として、ハッカ油やメントールがある。
― 問題 ―
高コレステロール改善薬は、腹囲を減少させる等の痩身効果を目的とする医薬品である。
答え、②.誤り ✕
解説
高コレステロール改善薬はあくまで食事・運動療法の補助として飲む薬である。
― 問題 ―
高コレステロール改善薬の配合成分であるビタミンB2の中のリボフラビンは、摂取により尿の色が黄色くなる事があるため、尿が黄色くなったら直ちに使用を中止する。
答え、②.誤り ✕
解説
リボフラビン摂取により尿が黄色くなることがあるが、副作用等の異常ではないため使用を中止しなくてよい。
― 問題 ―
LDL(低密度リポタンパク質)は、末梢組織のコレステロールを取り込み肝臓へと運ぶ。
答え、②.誤り ✕
解説
末梢組織のコレステロールを取り込み肝臓へと運ぶのはHDL(高密度リポタンパク質)であり、LDLはコレステロールを肝臓から末梢組織や血管壁へと運ぶ。
― 問題 ―
駆虫薬は腸管内に生息する虫体のみに作用する。
答え、①.正しい 〇
解説
そのため、虫卵や腸管内以外に潜伏する幼虫には駆虫作用が働かない。
― 問題 ―
浣腸薬の注入剤に配合されている成分は炭酸水素ナトリウムであり、坐剤に配合されている成分はグリセリンである。
答え、②.誤り ✕
解説
浣腸薬の注入剤に配合されている成分はグリセリンであり、坐剤に配合されている成分は炭酸水素ナトリウムである。
― 問題 ―
小腸瀉下成分であるセンナには、小腸でリパーゼの働きにより生じる分解物が小腸を刺激する特徴がある。
答え、②.誤り ✕
解説
小腸瀉下成分はヒマシ油である。
センナは大腸瀉下成分であり、その他にセンノシド、ダイオウがある。
― 問題 ―
副作用として便秘が生じることのある風邪薬の主な成分として、イブプロフェンがある。
答え、②.誤り ✕
解説
便秘が生じることのある風邪薬の主な成分はコデインリン酸塩であり、イブプロフェンは副作用として無菌性髄膜炎を起こすことがある。
― 問題 ―
医薬品には、食品と同一の安全性基準が要求される。
答え、②.誤り ✕
解説
医薬品については、食品よりもはるかに厳しい安全性基準が要求されている。
― 問題 ―
医薬品副作用被害救済制度の給付において、葬祭料の給付の請求期限は7年である。
答え、②.誤り ✕
解説
葬祭料の給付の請求期限は原則として死亡時から5年である。
― 問題 ―
緊急安全性情報は、A4サイズの黄色地の印刷物でイエローレターとも呼ばれている。
答え、①.正しい 〇
解説
緊急安全性情報はA4サイズの黄色地の印刷物で、安全性速報がA4サイズの青色地の印刷物(別名ブルーレター)である。
― 問題 ―
アルコール含有量が1回服用量中1mLを超える内服液剤(滋養強壮が目的のもの)は、アルコールを含んでいる事、及び含有分量が記載されている。
― 問題 ―
適切な保存条件下で、製造から4年を超えて品質や性状の安定が確認されている医薬品では使用期限表示の義務はない。
答え、②.誤り ✕
解説
製造から3年を超えて品質や性状の安定が確認されている医薬品で使用期限表示の義務はない。
― 問題 ―
一般用医薬品は、包装や容器にも保管に関する注意事項が記載されている。
答え、①.正しい 〇
解説
添付文書を見なくても適切な保管が出来る様に包装や容器にも記載されている。
― 問題 ―
解熱鎮痛薬は、頭痛の症状が現れる前に予防的に使用することが適切である。
答え、②.誤り ✕
解説
予防的に使用することは適切でなく、頭痛の症状が軽いうちに服用するのが適切かつ効果的である。
― 問題 ―
風邪の原因の8割が細菌感染である。
答え、②.誤り ✕
解説
原因の8割がウイルス感染であり、その他の要因として細菌感染、乾燥、冷気等がある。
― 問題 ―
全身作用が目的の医薬品では、その有効成分の大部分が小腸で溶出し、主に大腸で吸収される。
答え、②.誤り ✕
解説
有効成分の大部分が胃で溶出し、主に小腸で吸収される。
― 問題 ―
予防接種や点滴、塗り薬や湿布などの外用薬であれば、どのような種類の飲食をしても医薬品の代謝や作用に影響は受けない。
答え、②.誤り ✕
解説
点滴薬や外用薬であっても、飲食品の種類によっては医薬品の代謝や作用に影響を受ける。
― 問題 ―
アルコールをよく摂取する人は肝臓の代謝機能が低下してることが多いため、肝臓で代謝される医薬品は通常よりも代謝されにくい。
答え、②.誤り ✕
解説
アルコールを頻繁に摂取する人は肝臓の代謝機能が亢進してることが多く、肝臓で代謝される医薬品は通常よりも代謝されやすい。
そのため体内から医薬品が早く消失してしまい十分に薬の効果が得られないことがある。
― 問題 ―
牛乳や鶏卵などを原材料として作られている医薬品がある。
答え、①.正しい 〇
解説
そのため、牛乳や鶏卵などにアレルギーを持つ人は使用を避けなけらばならない。
― 問題 ―
健康維持の補助や健康増進が期待される、いわゆる健康食品は、法律上医薬品に区別される。
答え、②.誤り ✕
解説
健康食品はあくまでも食品のため、法律上医薬品に区別されない。
― 問題 ―
医薬品は少量投与であれば、長期投与しても特に副作用は起こらない。
答え、②.誤り ✕
解説
少量でも長期投与すれば慢性的な毒性が発現する場合もある。
― 問題 ―
医薬品は少量投与でも、胎児毒性や組織・臓器の機能不全を生じる場合がある。
答え、①.正しい 〇
解説
その他にも発がん作用が生じる場合もある。
― 問題 ―
汗腺のアポクリン腺は全身に分布し、エクリン腺は腋窩などの毛根部に分布する。
答え、②.誤り ✕
解説
アポクリン腺が腋窩などの毛根部に分布し、エクリン腺が全身に分布する。
― 問題 ―
小児の血液脳関門は未発達のため、医薬品の成分が脳の組織に到達しやすい。
答え、②.誤り ✕
解説
未発達のため医薬品の成分が脳の組織に到達しにくい。
― 問題 ―
交感神経が優位なとき、胃液分泌及び腸運動は亢進し、排尿筋の収縮により排尿が促進される。
答え、②.誤り ✕
解説
交感神経が優位なとき、胃液分泌及び腸運動は低下し、排尿筋の弛緩により排尿が抑制される。
問題文は副交感神経が優位の時に起きる現象である。
― 問題 ―
クリーム剤は患部を水から遮断したい場合に、軟膏剤は患部を水で洗い流したい場合に使用する。
答え、②.誤り ✕
解説
クリーム剤は患部を水で洗い流したい場合に、軟膏剤は患部を水から遮断したい場合に使用する。
― 問題 ―
偽アルドステロン症は、体内に水とカリウムが溜まり、体からナトリウムが失われることで起こる。
答え、②.誤り ✕
解説
体内に水とナトリウム(塩分)が溜まり、体からカリウムが失われることで起こる。
― 問題 ―
蟯虫の駆虫成分であるパモ酸ピルビニウムをのむと尿や糞便が黒ずむことがある。
答え、②.誤り ✕
解説
尿や糞便が赤くなることがある。
― 問題 ―
新生児は生後8週未満、乳児は生後8週以上2歳未満、幼児は2歳以上9歳未満、小児は9歳以上18歳未満を表す。
答え、②.誤り ✕
解説
新生児は生後4週未満、乳児は生後4週以上1歳未満、幼児は1歳以上7歳未満、小児は7歳以上15歳未満を表す。
― 問題 ―
薬局医薬品および要指導医薬品を繰り返し乱用することで慢性的臓器障害や薬物依存がおこるが、一般用医薬品ではおきない。
答え、②.誤り ✕
解説
一般用医薬品でも繰り返し乱用することで慢性的臓器障害や薬物依存がおこる。
― 問題 ―
医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準にはGVPが、臨床試験の実施の基準にはGPSPが制定されている。
答え、②.誤り ✕
解説
医薬品の安全性に関する非臨床試験の基準にはGLPが、臨床試験の実施の基準にはGCPが制定されている。
GVPは製造販売後安全管理の基準、GPSPは製造販売後の調査及び試験の実施の基準として制定されている。
― 問題 ―
医薬品投与量と効果または毒性との関係は、薬物用量の増加に伴い、非作用量から治療量を経た後に最大有効量となる。
答え、②.誤り ✕
解説
薬物用量の増加に伴い、無作用量から最小有効量を経た後に治療量となる。
― 問題 ―
ステロイド性抗炎症成分は、体の広範囲に生じたかぶれ・皮膚炎・湿疹等の一時的な皮膚症状の緩和を目的としたものである。
答え、②.誤り ✕
解説
体の一部分に生じた皮膚症状の緩和を目的としたものである。
― 問題 ―
角質軟化成分であるイオウは角質成分を溶解する。
答え、②.誤り ✕
解説
角質成分を溶解するのはサリチル酸であり、イオウは皮膚の角質層を構成するケラチンを変質させる。
― 問題 ―
配置販売業者またはその配置員が、都道府県知事から交付される身分証明書の有効期限は発行日から丸1年である。
答え、②.誤り ✕
解説
配置販売業者またはその配置員の身分証明書の有効期限は発行日から発行の日の属する年の翌年の12月31日である。
― 問題 ―
一般用医薬品の点眼薬には緑内障の症状を改善できるものはない。
答え、①.正しい 〇
解説
配合されている成分によっては緑内障を悪化させるものもある。
― 問題 ―
胃粘膜保護修復成分であるアルジオキサ・スクラルファートはマグネシウムを含むため、透析患者は使用するべきではない。
答え、②.誤り ✕
解説
アルミニウムを含むため、透析患者は使用を避けるのがよい。
― 問題 ―
一般的な妊娠検査薬は、月経予定日が過ぎてから約5日後の検査が推奨されている。
答え、②.誤り ✕
解説
月経予定日が過ぎてから約7日後(1週目)の検査が推奨されている。
― 問題 ―
組織修正成分であるプレドニゾロンは痔による肛門部の創傷の治癒を促進する効果がある。
答え、②.誤り ✕
解説
組織修正成分はアラントインであり、プレドニゾロンはステロイド性抗炎症成分である。
― 問題 ―
漢方処方製剤である防風通聖散は、腹部に内臓脂肪が多い肥満症に適した漢方である。
答え、②.誤り ✕
解説
腹部に皮下脂肪の多い肥満症に適する。
― 問題 ―
鉄分は空腹時のほうが吸収されやすいため、貧血改善のための鉄製剤は食前に飲むとよい。
答え、②.誤り ✕
解説
空腹時のほうが鉄分の吸収されやすいが、消化器系への副作用軽減のために食後に鉄剤を服用するほうが良い。
― 問題 ―
一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬は、急性・アレルギー性・慢性全ての鼻炎が対象である。
答え、②.誤り ✕
解説
急性やアレルギー性の鼻炎及びそれに伴う副鼻腔炎は対象であるが、慢性鼻炎(蓄膿症など)は対象外である。
― 問題 ―
殺菌消毒成分のクレゾールせっけん液
は一般細菌・真菌・結核菌・ウイルスなど全ての微生物に有効である。
答え、②.誤り ✕
解説
細胞壁を破壊することで効果を示すため、細胞壁をもつ一般細菌・真菌・結核菌には比較的有効であるが、ウイルスは細胞壁をもたないため大部分のウイルスには無効である。
クレゾール石鹸液 ➤ アルコール ➤ 次亜塩素酸ナトリウム ➤― 問題 ―
小児の疳を適応症とする漢方処方製剤(小児鎮静薬)は、1歳未満の乳児に使用してはならない。
答え、②.誤り ✕
解説
生後3か月未満の乳児に使用してはならない。
― 問題 ―
歯痛薬は歯がう蝕されたことにより発生する痛みを応急的に鎮痛する目的で使用する一般用医薬品であり、歯のう蝕を修復することができる。
答え、②.誤り ✕
解説
歯のう蝕を修復することはできないため、歯医者で治療を受けることが治療の基本である。
― 問題 ―
大豆油不けん化物(ソイステロール)は腸管におけるコレステロールの吸収を促進する。
答え、②.誤り ✕
解説
吸収を抑制する。
― 問題 ―
鎮咳成分であるコデイン・ジヒドロコデインは非麻薬性成分である。
答え、②.誤り ✕
解説
コデイン・ジヒドロコデインは麻薬成分であり、非麻薬性成分にはノスカピンやデキストロメトルファン等がある。
― 問題 ―
薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業のなかで、薬局と卸売販売業者はあらかじめ小分けにした医薬品を販売することが可能である。
答え、②.誤り ✕
解説
薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業全てにおいてあらかじめ小分けでの販売は無許可製造及び無許可製造販売にあたるため認められない。
― 問題 ―
薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて医薬品の分割販売をすることが可能である。
答え、②.誤り ✕
解説
配置販売業のみ分割販売をすることができない。
― 問題 ―
眼科用薬において、組織修復成分として配合されるのはベルベリンとプラノプロフェンである。
答え、②.誤り ✕
解説
組織修復成分はアズレン・アラントインである。
ベルベリンとプラノプロフェンは抗炎症成分であり、その他にイプシロン-アミノカプロン酸がある。
― 問題 ―
風邪薬にはウイルスの増殖を抑え、ウイルスを体内から除去する効果がある。
答え、②.誤り ✕
解説
風邪薬は諸症状の緩和を図る対処療法薬であり、ウイルスの増殖を抑えたりウイルスを体内から除去する効果はない。
― 問題 ―
風邪薬の配合成分であるサリチルアミドは、12歳未満の小児でインフルエンザまたは麻疹に罹患しているときは使用を避けたほうが良い。
答え、②.誤り ✕
解説
15歳未満の小児がインフルエンザまたは水痘(水疱瘡)に罹患しているときは使用を避ける必要がある。
同様にエテンサミドも使用を避ける必要がある。
― 問題 ―
風邪薬の配合成分であるブロムヘキシン塩酸塩は解熱鎮痛を目的としている。
答え、②.誤り ✕
解説
ブロムヘキシン塩酸塩は去痰を目的としている。
解熱鎮痛が目的の成分には、アスピリン・アセトアミノフェン・イソプロピルアンチピリン・イブプロフェン・エテンサミド・サリチルアミドがある。
― 問題 ―
風邪をひいた場合、発熱や咽頭痛、咳などと症状がはっきりしていても総合感冒薬を選択するのが最適である。
― 問題 ―
医薬品の副作用として出現する肝機能障害において、軽度の場合でも自覚症状があるため早期に発見することができる。
答え、②.誤り ✕
解説
軽度の肝機能障害の場合、自覚症状がなく血液検査(肝機能検査値の悪化)で初めて判明することが多い。
― 問題 ―
医薬品の副作用として出現する偽アルドステロン症とは、アルドステロン分泌が増加してないにも関わらず、体内にカリウムが貯留し、ナトリウムと水が体から失われることにより生じる病態のことである。
答え、②.誤り ✕
解説
偽アルドステロン症とは、体内にナトリウムと水が貯留し、カリウムが体から失われることで生じる病態である。
― 問題 ―
坐剤の有効成分は直腸内壁の粘膜から吸収されて容易に循環血液中に入り、臓器による代謝を受けることなく全身に分布する。
答え、①.正しい 〇
解説
直腸粘膜には静脈が豊富に分布するため、全身作用が速やかに発現しやすい。
― 問題 ―
坐剤の有効成分は直腸内壁の粘膜から吸収されて容易に循環血液中に入り、臓器による代謝を受けることなく全身に分布する。
答え、①.正しい 〇
解説
直腸粘膜には静脈が豊富に分布するため、全身作用が速やかに発現しやすい。
― 問題 ―
内服以外の用法により使用される医薬品の中には、適用部位から有効成分を吸収させ、全身作用を発揮させることを目的とするものがある。
答え、①.正しい 〇
解説
解説:具体例として舌下錠がある。
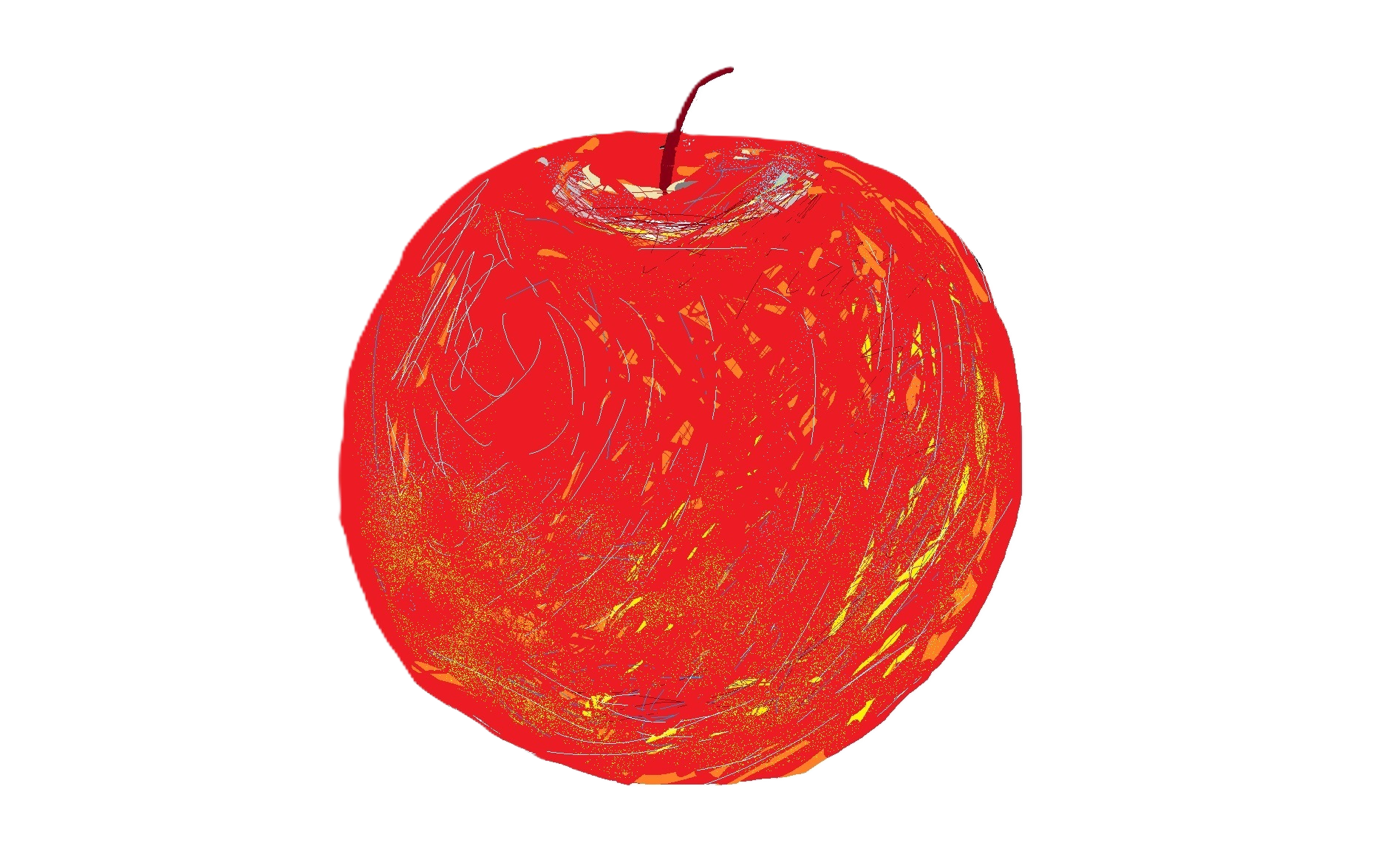
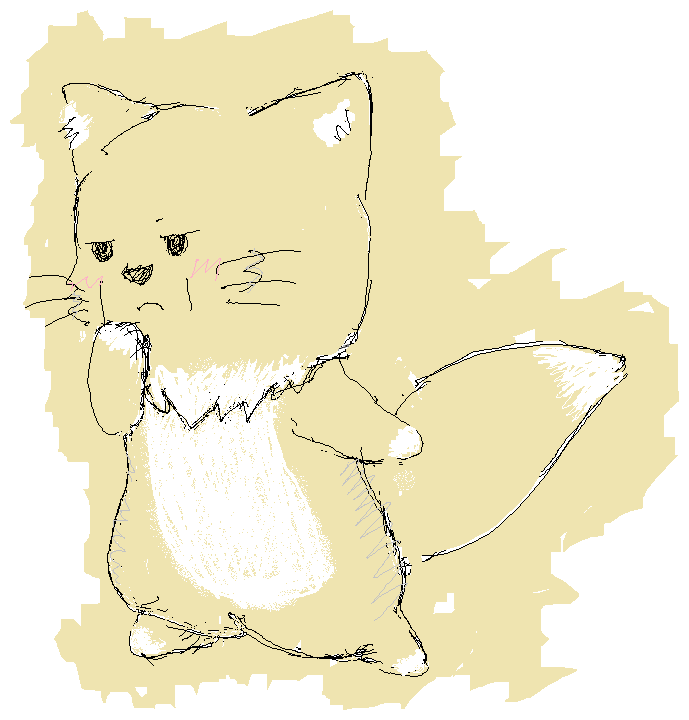
広告
参考
・医薬品登録販売者試験対策ズルい!合格法出る順過去問題集Z超 株式会社医学アカデミーYTL.
・TRIPS LLC.(2022).登録販売者 過去問 全問解説(バージョンン7.48.0).RRIPS LLC.https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.trips.shikakutorokuhanbaisha&hl=ja&pli=1